この記事は2023年10月にサービスが終了した読書サイト『シミルボン』に投稿していた記事である。ボクの日記から推定すると、記事の公開は2020年11月頃。
デュルケムの『社会学的方法の規準』(1895年)を読む試みです(第2回/全3回)。第1回はこちら。
第三章 正常なものと病理的なものの区別にかんする諸規準
第三章は本書の肝だと思うので、少し詳しく取り上げる。
実践の学としての社会学
ここまでデュルケムは社会学が科学としての性質を獲得できるように、社会学独自の研究対象とその観察における諸規準について述べてきたが、彼は社会学が単に社会的諸事実の観察や説明に留まるべきだとは考えていない。むしろ、社会学は「いかにあるか」という問題だけでなく、「いかにあるべきか」という問題をも探究できなければならない、と宣言している。
ある理論にしたがえば、科学というものは、われわれがなにを欲すべきかについてはいささかも教えてくれない。〔中略〕科学の観点からすれば、善も悪も存在しない。いかにも、科学は諸原因からどのようにその諸結果が生じるかを教えることができるが、いかなる目的が追求されるべきかについては語ることができない。〔中略〕とすれば、およそ科学は、いっさいの実践的な効力を欠くことになるか、もしくはそれに近い状態となり、結局は大した存在理由をもたないことになる。というのも、現実についてわれわれの獲得する知識が、生活のなかで役立つことができなければ、現実を知ろうとつとめることにどれほどの意味があろうか。(pp.121-122)
役に立たない知識は探究するに値しない、などと聞くと、穏やかな話ではない。昨今の文系不要論や基礎研究の低迷とも関わってくる話だろう。結局、探究を始める前にその探究によってもたらされる知識が「役に立つ」か否かを判定することは人知の及ばぬことだと私は思うが、デュルケムは科学には実践的な知識をもたらすという使命があると考えているようだ。
社会学的現象の正常/病理的の区別
では、社会のあるべき方向はどのようにして見定められるのだろうか。デュルケムは生物学における健康/病の区別をアナロジーとして、社会的事実に関する正常/病理的という区分を導入し、その区別を可能にさせるような次の基準にしたがって判断すべきと書いている:
もっとも一般的な諸形態を示している事実を正常的とよび、他方を病態的もしくは病理的と名づけることにしよう。(p.134)
つまり、ある社会的事実が一般的、平均的なものであればそれは正常で、そうでなければ病理的だというわけだ。このデュルケムの正常/病理的の判断基準の特徴は、それが相対的な基準である、という点にある。何が正常で病理的であるかは絶対的に決められるものではなく、あくまでその社会の種ごとに異なったものでありうる、というのだ。
しかし、デュルケムはこれだけでは正常/病理的の判断基準としては不十分であることを認める。ある事実が一般的であるなら、それを一般的たらしめる根拠を探究し、それがその社会を存続させる条件に根差していることを確かめよ、と言っている。というのも、一般的な社会的事実であっても、単に「正常性の外観」を保っているにすぎず、社会の要求に応えていないということもあるからだという。
犯罪は「正常」か
デュルケムは正常/病理的の判断基準の適用例として、犯罪を取り上げる。前節で述べられたことを踏まえると、犯罪が正常的であるかどうかを確かめるには、次の2点について確認すればよい。
1.犯罪はその社会で一般的なものであるか。
2.犯罪はその社会で要求されているものか。
この2つの基準について、どちらもYesなら正常、少なくとも1つがNoなら病理的と判断される。順にみてみよう。
まず、犯罪は「たんにかくかくしかじかの種にぞくする諸社会の大部分にみとめられるといったものではなく、あらゆる類型のあらゆる社会においてその存在が観察されている」(p.150)。これには異論がないだろう。したがって、犯罪は「正常」と判断されるための1つ目の基準を満たしている。
では、2つ目の基準はどうか。デュルケムの結論を先取りすれば、次のようになる:
犯罪は、必然的かつ必要なものである。すなわち、犯罪はいっさいの社会生活の根本的諸条件に結びついており、しかもまさしくそのために有用なのである。(p.157)
つまり、デュルケムは第2の基準もクリアしているので、犯罪は「正常」な社会的事実だと言っている。しかし、この結論はいかにも「非常識」なものである。デュルケム自身、「この帰結は一見したところじつに意外なものであるため、筆者自身も、それも永いあいだ、当惑させられていたほどである」と書いている。にもかかわらず、彼は犯罪は社会にとって必要なものであると結論づけた。彼がいかにこの結論に至ったのか追ってみることにしよう。
デュルケムによれば、ある行為が犯罪と見なされるのは、その行為が社会の共同意識を害するからだという。したがって、もしある社会から犯罪が一掃されるとすれば、その社会の成員の誰もが、社会の共同意識を害するような行為をしないこと、が必要となる。しかし、そのような社会は第一に実現不可能であり、第二に望ましくないとデュルケムは主張している。まずは第一の点に関して、少し長いが引用する。
たとえば、盗みも、たんなる無作法な行為も、他者の所有の尊重というひとつのおなじ愛他的感情を傷つけるにすぎない。ただし、このおなじ感情を傷つけるのに、それが前者の行為ではより強く、後者の行為ではより弱くなされるということである。そして他方、平均的な人びとの意識においては、この感情が、二つの侵害行為のうちのより軽微な侵害をも痛切に感じるほどの強度にまで達していないため、そうした侵害はより大目にみられることになる。無作法な者が非難だけですまされるのに、窃盗をはたらく者が罰せられるのはこのような理由による。ところが、もしもこのおなじ集合的感情がいっそう強められて、人を盗みにいたらしめるような傾性を万人の意識のうちで抑えるまでになれば、それまではわずかにしか感じられなかった諸〻の侵害が、この感情によってより敏感にとらえられるようになろう。その結果、集合的感情は、これらの侵害により強く反応するようになり、いきおいこれらの侵害はより激しい非難の対象となって、そのうちの若干は、かつてはたんなる道徳的過誤であったのが、犯罪の状態へと移行していくことになろう。(pp.154-155)
かつては大目に見られたことも、人々の意識の変化によって犯罪行為とされるようになることがある。例えばパワハラ・セクハラ、DVなどはかつてはそれを表す語彙さえまともになかったものが、社会一般の意識の変化によって問題視されるようになったものではないだろうか。あるいはこのコロナ禍で、不特定多数が利用する公共空間ではマスク着用がマナーとなりつつあるが、極端な状況になればマスクを着用せずに出歩くことが違法行為とされるようになるかもしれない。
結局、より一般感情を害する行為ほど厳しく取り締まられるのだから、仮に現在の大悪が一掃されたとしても、現在の小悪が大悪に化してしまう。人間が生物としてネガティブな感情を抱く性向を有する以上、それは避けられないことなのだろう。
ところで、こんな疑問もあるかもしれない。社会の全員が、共通の道徳意識に従って振る舞えば、だれも共同意識を害する行為をしないのではないかと。例えて言えば、社会の人々がみんな自分とそっくりそのままの道徳意識を持っていて、そこから逸脱しようとしないのだ。こんな社会なら、犯罪なるものはなくなる。それは論理的には可能だとデュルケムは認める。しかし、そうなると誰も共通意識から逸脱しないので、社会の共通意識自体も変化しなくなる。となると、道徳意識は低下することもないが、高まることもない。そんな社会は望ましくない、というのがデュルケムの考えだ:
およそ道徳意識が変化しうるためには、個人の独自性が実現されることが必要である。とすれば、世紀に先んじることを夢見る理想主義者の道徳意識が表明されるためには、その時代の水準にも後れをとっている犯罪者の道徳意識の存在をもゆるされなければならないことになる。(p.158)
かつて法の下の平等や思想・信条の自由、学問の自由なるものが「理想」でしかなかった時代にあって、こうした理想を追求する者は異端者であり、「犯罪者」だった。犯罪のない社会というのは、こうした理想を掲げて行動する者も皆無な社会なのだ。現状の社会が金輪際変わらず、よりよい社会は実現できるという希望を抱く余地すらない社会なのだ。このような観点に立って、デュルケムは犯罪を「有用」なものとして位置づけている。
以上の検討から、犯罪者は「社会生活の正常な主体」だとデュルケムは述べているが、だからといって「犯罪者が生物学的・心理学的観点からみて正常な構造をもった一個人であるということにはならない」し、「犯罪が正常社会学にぞくする一事実であるからといって、これを嫌悪する必要がないということにはならない」点に注意が必要だ。誤解してはならないが、デュルケムは犯罪を弁護したいのではない。あくまで社会的視座の下で「犯罪」をという社会的事実を客観的に研究した結果、デュルケムの「正常/病理的」区分に従えば犯罪は正常な社会的事実と判断された、ということだ。そこからどのような実践上の意味が見いだせるのかは、読者にゆだねられている。
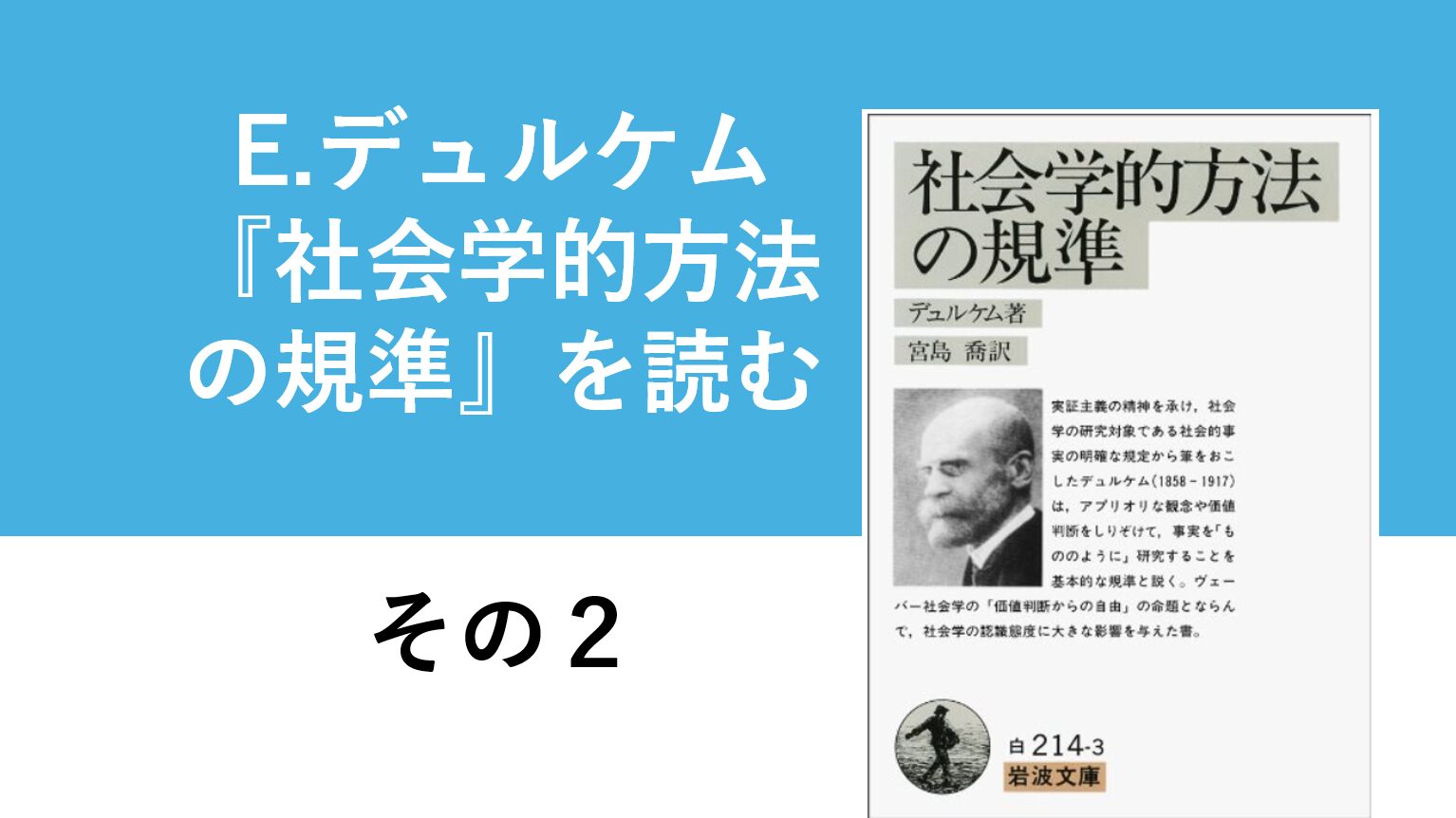


コメント